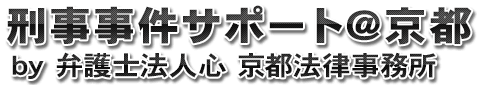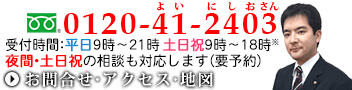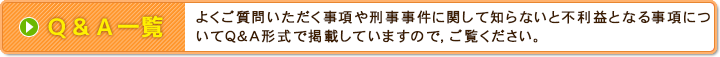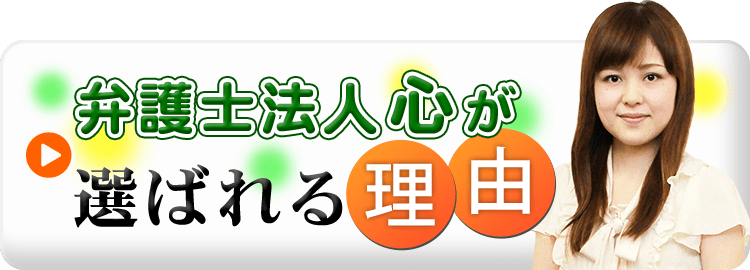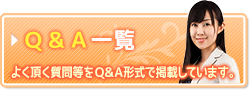保釈が認められる基準
1 保釈で誤解されやすい点
「保釈」という言葉は、一般にも知られた言葉だと思いますが、よく勘違いされている点があります。
まず、起訴される前は、保釈という制度はないということです。
逮捕された方に面会に伺うと、すぐに保釈して欲しい等と言われることがありますが、保釈という制度は、起訴されて、裁判になることが決定した後の制度です。
なお、起訴される前の身柄釈放のための手続きは、別途あります。
また、保釈というと、保釈金という言葉のイメージが強いからか、お金さえ準備できれば、保釈が認められると勘違いされている方も散見されます。
確かに、最終的に保釈によって釈放されるには、裁判所が定めた保釈金の納付が必要となります。
しかし、実際は、保釈というのは、お金さえ準備すれば、必ず認められるわけではありません。
裁判所が保釈を相当と認めた事案でなければ、いくら保釈のためのお金を準備しようが、保釈されることはありません。
当該事案は、保釈を認めても問題ないという裁判所の判断を前提に、保釈金がいくらかにするかという話になりますので、そもそも、裁判所が当該事案は保釈することは相当でないと判断すれば、保釈金の話にならないのです。
2 保釈が認められる基準
裁判所が保釈を認める基準は、刑事訴訟法第90条にあります。
刑事訴訟法90条には、「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御上の不利益の程度を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる」と規定されています。
上記条文の中で、保釈許可、不許可の判断に重要なのは、被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度であると思います。
例えば、覚醒剤の所持罪や使用罪の事案で、被告人が初犯で、容疑を認めていた場合、問題なく保釈は認められることが多いです。
これを被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度にあてはめると、被告人が初犯の場合、判決は、執行猶予が付されることが予想される、つまり実刑になる可能性が低く、実刑になることをおそれて、逃亡するおそれは低いと判断されやすいでしょう。
そして、容疑を認めている事件であれば、被告人が証拠隠滅行為をする可能性は、それほど高くないと判断されることが多いでしょう。
以上のように、覚醒剤の所持罪や使用罪の事案で、被告人が初犯で、容疑を認めていた場合、問題なく保釈は認められることが多いのは、逃亡及び罪証隠滅のおそれが高くない事案であることが多いからであるといえるのです。