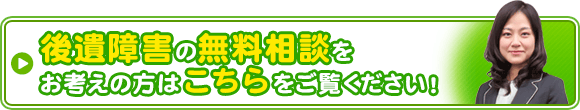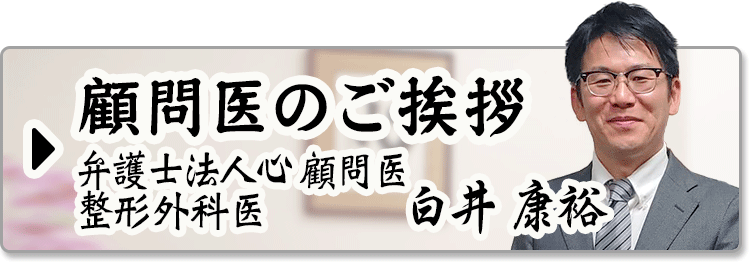歯の損傷と後遺障害認定に関するQ&A
歯の後遺障害にはどのような等級がありますか?
交通事故で顔面や頭部に衝撃が加わって歯が折れるなどし、歯の喪失や著しい欠損が生じた場合には、歯牙障害として歯の後遺障害が認定されることがあります。
歯牙障害の後遺障害は、10級4号、11級4号、12級3号、13級5号、14級2号が認定される可能性があります。
他のケガにより歯の状態に気づくのが遅れたり後回しになったりすることもありますが、事故との因果関係が曖昧にならないようにできるだけ早く歯科医院を受診してください。
歯の後遺障害は、基本的には、歯の損傷の程度と損傷した本数で後遺障害認定が行われています。
10級4号は14歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの、11級4号は10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、12級3号は7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、13級5号は5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、14級2号は3歯以上に対し歯科補綴を加えたものです。
歯の後遺障害診断書は、通常の後遺障害診断書の書式とは別の書式がありますので、注意が必要です。
歯科補綴とは何ですか?
後遺障害の対象となる歯科補綴は、現実に、歯牙そのものを歯根に至るまで喪失した場合、または、歯冠部分(口腔内で歯肉から露出している部分)の体積の4分の3以上欠損した場合に、喪失または欠損した歯を人工物で補う方法で歯を補強する歯の治療法です。
通常は、義歯(歯を補うための人工の歯)、クラウン(歯全体を覆う被せ物)、インレー(つめ物)、などの人工物で、喪失または欠損した歯を補います。
後遺障害の対象となるのは、永久歯だけで、乳歯や親知らずは、後遺障害の対象となりません。
歯の後遺障害申請で気を付けることはありますか?
歯の喪失や欠損は、事故の衝撃自体から歯がなくなったり、欠損したりした場合だけでなく、治療として抜歯せざるを得ず抜歯した場合や、治療の過程で削ったことにより欠損した場合も含まれます。
例えば、ブリッジ(失った歯の両隣の歯を削り土台にして真ん中の歯を支える治療方法)を装着する際に、両隣の歯を削ったことにより歯冠部分の体積の4分の3以上を削った場合には、失った歯に加えて両隣の歯である2本の歯にも歯科補綴を加えたものとされます。
事故前から歯科補綴を加えた歯が存在した場合には、既存障害として扱われ、上位等級の金額から既存障害の等級の金額を差し引いた金額が支払われることになります。
例えば、もともとの虫歯で3本の歯を歯科補綴していた方が、交通事故により新たに4本の歯に歯科補綴を受けた場合には、7本の歯に歯科補綴を加えたものとして後遺障害としては12級3号が認定されますが、12級の損害賠償金額から14級の既存障害分の損害賠償金額を差し引いた金額しか、賠償金は請求できません。
例えば、先ほどの事例で12級が認定されても、後遺障害慰謝料は、12等級の慰謝料(約290万円)から14等級の慰謝料(約110万円)を差し引いた金額(約180万円)しか請求できません。
他の後遺障害による損害も同様です。
歯の後遺障害逸失利益については、歯科補綴を加えたことにより機能が大幅に回復することも多いため、労働能力が喪失したのかどうかが争われることが多くなっています。
歯の後遺障害逸失利益については、具体的な支障を丁寧に立証していくことが必要です。
歯の損傷による後遺障害認定は非常に複雑で、様々な争点も予想されます。
交通事故で複数の歯に損傷が生じた場合には、なるべく早く弁護士にご相談ください。
後遺障害の認定がされない場合はどうすればいいですか? 交通事故の高次脳機能障害の症状固定時期はいつごろになりますか?