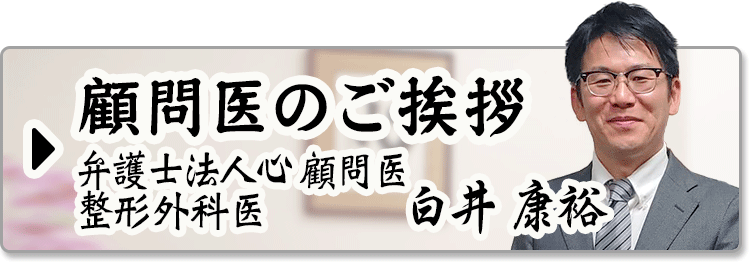交通事故の高次脳機能障害の症状固定時期はいつごろになりますか?
1 高次脳機能障害の症状固定時期
交通事故の高次脳機能障害の症状固定時期は、個人差はありますが、事故から1~2年経過してから症状固定と判断されることが多くなっています。
また、子どもの症状固定時期は遅くなる傾向が、高齢者の症状固定時期は早くなる傾向がみられます。
高次脳機能障害は、記憶、思考、判断などの高度な脳の機能が正常に働かなくなる病気です。
高次脳機能障害で発症する症状は人によって様々で症状経過は複雑です。
症状固定時期については、主治医にも相談しながら慎重に決めていきます。
2 高次脳機能障害の治療と症状固定
症状固定は、治療をしても一進一退となり効果がみられず、症状の改善が見込めなくなる状態です。
交通事故による高次脳機能障害の場合は、医学的には頭部外傷後の脳室拡大は1か月~数か月(多くは3か月)で完成するものとされており、この間は脳の損傷が進んでいる状態です。
脳室拡大等の脳の症状の進行が止まった後は、リハビリにより高次脳機能障害の症状が改善して機能が回復していき、その後改善が見られなくなったら症状固定です。
脳の症状の進行が止まってから1年~1年半程度の間は、リハビリにより高次脳機能障害の症状が改善していく治療期間とされますので、改善が見込めなくなる症状固定のタイミングは非常に重要です。
また、特に子どもの場合には、成長過程での脳や性格の変化もあり、脳機能の変化について一定期間の経過観察が必要で症状固定の見極めも難しいことから、慎重な判断が必要です。
3 高次脳機能障害の要件
交通事故における高次脳機能障害については、脳の器質的損傷を示す診断名があり、受傷後の一定の意識障害が発生し、脳の損傷が画像等で確認でき、一定の症状が発生することが必要です。
交通事故による外傷性の脳損傷後は、MRI画像で特徴的な器質病変が認められることがあり、経時的なMRI画像上にこの特徴的な器質病変が認められれば、交通事故による脳機能障害として認められやすくなります。
そこで、交通事故の初期からきちんと被害者の状況を記録し、MRI撮影を行っておくなどしておかないと、高次脳機能障害が発生していることや発生した高次脳機能障害が交通事故を原因とするものであると認められず、大変なことになってしまうかもしれません。
また、高次脳機能障害が疑われる症状を家族が記録したり、カルテ上に残っていることも重要です。
歯の損傷と後遺障害認定に関するQ&A 交通事故で通院する病院を変更できますか?